生産形態をわける生産と受注のタイミング
製造業の生産形態について、一般的には、「生産をいつ開始するか」という視点で、受注生産と見込生産の二つに分類されます。
受注生産は顧客から注文を受けてから生産を開始する形態であり、見込生産は顧客からの注文を受ける前に生産を開始する形態です。
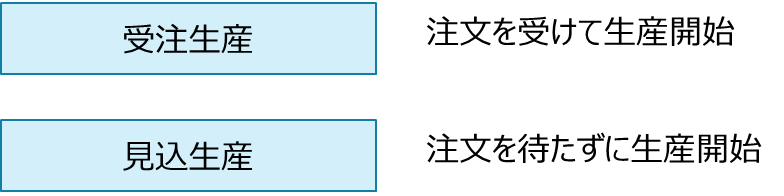
受注生産の製品は、例えば特殊な工作用機械や航空機用部品のように、一製品ごとに顧客の要望により製品仕様が異なるものが該当し、顧客の要求する仕様を確認した上で、個別対応型の設計・製造を行います。仕様が製品個々によって異なるので、注文を受けてから製品が完成するまでの時間(製造リードタイム)は相対的に長くなります。
これに対して、見込生産は、家電製品や自動車など製品の仕様があらかじめ決まった標準品で、一度に一定量を生産する量産型の製品が代表例になります。製品ごとに仕様の違いが少ないため、受注生産の製品に比較して、製造リードタイムは短くなります。
この二つの違いは単に、生産開始のタイミングだけの問題にとどまりません。受注を受けてから生産をするのであれば、顧客との取引が成立した上での生産なので、出来上がった製品の買い手があらかじめ決まっていることになります。
一方で、見込生産の場合は、顧客からの注文はまだ受けていないものの、自社の判断と責任によって生産を開始することになります。顧客が実際に製品を買ってくれないかもしれませんし、たとえ買ってくれたとしても、全量さばけるとは限りません。したがって、売れ残った製品は自社の在庫となり、原材料費用、人件費、機械稼働に伴うエネルギー費用などのコストを回収できず、損失となるリスクがあります。
逆に、予想以上に顧客からの注文数が多いと製品が足らなくなることもあり得ます。製品がなければ顧客は、購入を見送るか、あるいは競合他社の製品を購入するかもしれず、販売機会の逸失につながります。
この様に、見込み生産の場合は、生産数量の決定は、リスクを伴う経営上重要な意思決定となります。
過去においては、企業が採用する生産形態は、受注生産と見込生産とに明確に分かれていました。ところが、最近では両者の中間の生産形態も増えてきました。これには理由があります。
受注生産ではリードタイムが長いことから、短納期を求める顧客の要望を必ずしも満たすことはできなかったり、見込生産では、自社が作成した販売見込が狂ったときの在庫リスクがあまりにも大きかったり、とそれぞれ課題がありました。そこで、完全な受注生産、見込生産ではなく、顧客のニーズと自社のリスク低減の両立を図るために両者の折衷案のような中間の形態も現れるようになっています。
受注生産といっても、仕様が共通な部分については、部品や資材を調達して一定数を生産しておき、仕様が異なる部分のみを顧客からの注文を受けて製造する半見込生産型の形態は完全な受注生産と比べて、全体の製造リードタイムを短縮する狙いがあります。
あるいは、見込生産において、正式な受注でないものの、顧客の生産計画の情報を取り込み、限りなく受注に近い内示を受けて製造を行うという例もあります。これは受注確度を高めて、自社の在庫リスクを低減するねらいがあります。

